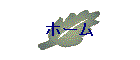
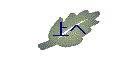
行 者 列 伝
![]()
覚明行者
覚明行者は享保3年(1718)3月3日に、尾張国春日井郡牛山村の農夫清左衛門の子として生まれ、母を千代といった。
家が貧しかったので、土器野村の新川橋辺の農家に引きとられて養われたという。
木曽の大桑村上郷の田沢家の伝承によると
「覚明様はもと魚商人で名古屋の方から木曽へ行商に荷物をかついできて家(田沢家)へもよく泊ったり休んだりしていった。
木曽の地理はとてもくわしかった。
そのうちどうしたことか、さっばりこないと思っていたら、何年かたって今度は行者になってやってきた。」といっている。
行者が御嶽登拝を目指して木曽へ来て、第1回の登山をおこなったのは天明5年であり、
連城亭随筆の筆者の村へ覚明行者として訪れたのは天明6〜7年のことであるから、
行者の名が御嶽登山をおこなって後になってからその郷里にも知られるようになったものであることがうかがわれるものである。
王滝村滝氏所蔵の『神社留記』によると
天明4年、5年の両年にわたって黒沢村の武居家へどこの国のものかはっきりしない坊主が来て
御嶽登山を許可してくれと頼みこんできたが、
登拝は古来より百日精進の重潔斎でなくてはならないとして許可しなかったところ、
天明5年にはついに許可を待たずに6月4日8人、14日には30人余り、28日には7、80人余りが
御嶽山大先達覚明という旗をおし立てて登ったとしているから、
天明4年に御嶽登山の念願のもとに黒沢村へ来たものであることが知られる。
なおこの記録によると「此坊主名古屋通り松にて3年以前(天明2年)御追放にて山賊の張梵切支丹の様相見へ申侯。」とあるから、
この以前から行者として相当の活動をしていたことが知られるし、
名古屋を追放された行者は中山道を下って木曽に来たものと考えられる。
大桑村野尻には覚明行者が古瀬屋に宿泊し、古宮の滝という所で修行をしたことがあると伝え、
また行者は福島の願行寺(福島に居館した、木曽代官山村氏が比叡山や東叡山にならってその鬼門鏡護とした天台宗の寺院)
覚円法印に師事したと伝えているし、
さらに開田村の西野、未川には、覚明行者が布教の途次この地に赤松の生えているのを見て稲作の可能を説き、
開田を勧めたとしている伝承があり、村の作次郎という、福島・西野間の持子をしていた者が行者の強力をつとめたという伝承もあって、
御嶽登山をおこなう前、行者が山麓諸村落の間を布教して回ったものであることがうかがわれる。
『連城亭随筆』には行者が川へ棒を浮かべてその上を伝って渡る術を持っていたことを述べており、
また王滝村の『神社留記』にも
「霞を自在に仕り、御体も己が自由自在に仕り、怪敷き事にて諸人の目を驚し申候」とあるから、
その法力がすぐれており、山麓の村々においても多くの信徒を得ていたものであることがうかがわれる。
行者が初めて黒沢へ来たときの様子を伝えるものとして
「黒沢村の某が福島の半夏の馬市に出掛けての帰りみちに合戸峠で覚明行者に行合い黒沢へ案内して来た。
そしてねんやへ連れていって登山のことをたのんだが
百日の精進をしたものでなければ登らせるわけにはいかないといって許されなかった。
それで田中の庄屋のところへいったが田中でも、
ねんやと福島の代官様の許しがなければ到底登山することはできないといって諭したので、
あきらめて帰っていった」
という口碑が残されているが、鎌倉時代以来御嶽の支配者としての地位を与えられていた黒沢村の神官武居家では、
軽精進によるみだりな登拝は数百年来続けられてきた重潔斎による登拝行事の慣例を破るものであり、
御嶽の神威を犯すおそれがあるとして行者の請願を却下したものである。
しかして行者は御嶽軽精進登拝の念願を捨てることができず、
翌天明5年(1785)6月登山を強行するに至ったものである。
この間の事情は「覚明行者による黒沢口登山道の改修と軽精進登山の許可」のところで詳しく述べたとおりである。
天明6年行者はさらに信徒を引きつれ登拝をおこなうとともに、
黒沢村薮原の仙長九郎等の協力を得て登山道の改修のことにもあたろうとしたが、
この事業遂行の中途で病のおかすところとなり、
ついに天明6年6月20日御嶽山の二の池の畔で入定しその生を終えるに至ったものである。
ミイラ化したその遺骸は信者たちによって9合目に葬られた。
現在の覚明堂の場所がそれである。
行者の没後その功績が認められ、寛政4年に至って武居家より軽精進登拝の正式許可があり、
これによって御嶽信仰が木曽一円の信仰から全国的な信仰へと拡大されていく端緒が作られるようになった。
この偉大なる功績に対し、嘉永3年(1850)7月覚明行者に対して、上野東叡山日光御門主より菩薩の称号が授けられている。
黒沢の赤岩巣橋の霊神場の覚明行者の霊神碑はこのとき建立されたものである。
![]()
普覚行者
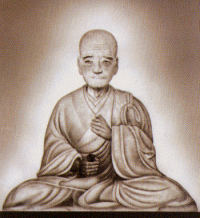 普寛行者は享保16年に武州秩父郡大滝村の落合という所で、木村信次郎の子として生まれた。
普寛行者は享保16年に武州秩父郡大滝村の落合という所で、木村信次郎の子として生まれた。
幼名を好八といい、幼にして浅見家の養子となり、長じて左近と称した。
少年の時代より剣法を好み、その業は相当進んでいたようである。
のち江戸に出て八丁掘の法性院を頼って剣道、漢学に励んだといわれている。
明和元年8月致仕して郷里に帰り、三峯山に登り観音院の日照の門に入り、剃髪して普寛と改め修験の道に励むこととなった。
師のもとにあること3年、その間台密二教の奥義を究め、明和3年8月権大僧都に昇格し、本明院と号し、
再び江戸に入り、先師法性院の法統を継いだ。
院は聖護院派に属していた関係から、府下の聖護院派の修験長となり、天明2年10月伝燈阿閣梨に進んだ。52歳のときという。
しかしながらこの年「其の志にあらず」といって修験長の職を退き、
「庶人の為に病厄を戒除する」と称して深山にこもって木食、水飲の修行に努め、
その後諸国周歴の旅に出たといわれている。
この後また江戸に帰って八丁堀の法性院に住んで剣道の指南などもしていた。
江戸八丁掘の法性院にあって、剣法指南の傍ら、庶民のために病気その他の祈祷をおこなっていたもののようで、
京橋八丁掘の和田孫八方(後の明岳院広山)で石に呪文を唱えながら少女のあざを治したといったことが江戸市中の評判となり、
後に御嶽登山の同行として加わった住吉町の三河屋庄八、高砂町の秩父屋歳次などの
当時の有力な商人たちの帰依を受けるようになったものである。
行者の御嶽登山の動機について諸書はみな四国辺路の途上老僧から御嶽登拝のことを授けられたことにしているが、
しかしこれは後になって伝説化されたもので、
寛政2年5月に秩父にあって、木曽王滝村出身の日雇頭与左衛門の失明を救ったときの与左衛門の話に暗示を受け、
前記の記録のように寛政4年6月、三河屋庄八等とともに、与左衛門を頼って王滝村を訪れ、
ついに王滝口からの新ルート開拓に成功するに至ったものである。
しかしながら、与左衝門は御嶽登拝の経験がなかったので、翌寛政5年の第2回登山には、
同じ王滝村の出身で江戸霊岸島の材木商桝屋庄三郎方で代人として活躍していた吉右衛門を案内に頼んでいる。
吉右衛門は後に普寛の四天王といわれ吉神行者と称した人である。
当時与左衛門もそうであったように、木曽山で杣、日雇などの仕事に携わっていた人々の中で、優秀な技能を持った者は、
木曽谷を出て、他地方の伐木運材の頭領となったり、
江戸や名古屋の材木商の代人や番頭等となって出向して活躍している例が多く見られるが、
吉右衛門もその1人であり、江戸に出ていたものであることが知られる。
しかして吉右衛門は与左衛門と違って、郷里王滝村にあった当時道者として御嶽登拝の経験を持っており、
普寛行者がこわを見込んで第2回の登山から、案内人として強引に頼みこんでいることがうかがわれるものである。
行者はその後、御嶽講社の結衆に努め、江戸を中心として関東地方1帯に広く御嶽信仰を押し広めたが、
さらに越後の国の八海山、武蔵の国の意和羅山、上野国利根郡の武尊山も開闢し、その分神を御嶽山へ勧請している。
享和元年9月、布教の途上、武州本荘宿の米屋弥兵衛方に止宿し、
滞在中病気となり9月10日
「なきがらは いつくの里に埋むとも 心御嶽に
有明の月」
の辞世の歌を遺して遷化した。
行年71歳。
その遺骨は遺言によって、御嶽山麓花戸と郷里三峯山麓、遷化の地 本庄宿、それに江戸法性院墓地に分骨埋葬された。
本庄宿、それに江戸法性院墓地に分骨埋葬された。
行者の50年忌の嘉永元年6月、王滝村花戸に江戸高砂講によって「開闢木食普寛行者」の碑が建立されている。
『西筑摩郡誌』には「夫れ御嶽の開道ありしより、未だ百年に満たずして、信徒日に増加し、所在社を結ぶもの二十八州に渉り、例歳登山する者六万を下らず、昔日の寒郷今乃ち福地となり、附近亦其沢を受く、是全く普寛の功徳に頼る衆尊崇以て霊神となすo」とその御嶽信仰全国普及の功績を顕彰している。
「御嶽の信仰と登山の歴史」-生駒勘七著(第一法規)
![]()