道者たちの精進期間は格式によってそれぞれ違っていた。
本精進は4月8日から100日間。
湯道精進・合力精進・女精進(井田道者)は5月5日よりはじめて75日間の潔斎をおこなっている。
精進に入ると、この日より衣類はみな白衣を用い、食事道具も一切新しいものを使い、
家族とは別火で物を食べている。
精進期間中は男女同きんを禁じ、
五辛(にんにく・らっきょう・ねぎ・ひる・にら)と魚鳥の食用禁止等
かなり厳しい潔斎がおこなわれていたものである。
登山の時期が迫った6月5日には道者たちが全員寄合って、
おひねりを作ったり御神酒を竹筒に詰めること、
その他登山の諸道具の準備をおこない、
用意ができるとこれを、
里宮へ持っていき、
湯立神事をおこなってきよめることをしている。
さらに6月6日から13日まで里宮で礼拝行事がおこなわれているが、
これを千度の拝といい、
6月6日昼と12日の朝・昼・夕と6回で延べ673度の礼拝をおこなっている。
この間松久沢川という所で水垢離をとっている。
また登拝前に御嶽三十八座のうち
山麓に所在する
若宮・本社・牧尾・樽沢(アンバの滝、現在は牧尾ダム建設で水没)・白川・岩戸等の
諸社を巡拝することもおこなわれていたものである。
登拝は6月14日朝、子ノ刻に、黒沢・王滝それぞれの里宮を出発して、
黒沢の白川で水垢離をとり、飯の王子で昼食をとり、
その後、扇ノ森・千本松・西ノ除・大江権現などの行場を奉幣しながら登り、
この日は大江権現(黒沢村の道者は湯権現)で一泊、
翌15日は再び山内の行場を奉幣しながら、
山頂の日ノ権現、王の権現を参拝して下山している。
当時は登山道もあってないようなもので、年一度の登拝は容易なことではなく、
その上このような厳しい重潔斎をおこなっていたものであるから、
神沢吐口が『翁草』に書いているように、
 登拝者の数はごくわずかなものであったことが知られる。
登拝者の数はごくわずかなものであったことが知られる。
なお登拝できない者の代参といったことも、道者はおこなっていたもののようで、
滝氏の記録の中に、
代参の礼金として「金子壱両、外に扶持米三歩」を必要としたことが記されている。
登山の携行品として、
小大麻袋・大大麻袋・杖・桧笠・菅みの・わりご弁当・たい松(十五たい)・わらじ(五足)・米一升五合・味噌少々をあげており、大麻袋を大小携行しているが、大小麻袋を「ぜん袋」ともいったとある。これは袈裟掛けに背負うようにできている。
杖は椹木と書いてあるが、他のものには桧または椹とあり、どちらかを使ったようである。現在の金剛杖である。
わらじは五足用意したようであるが、『御嶽由来伝記』にはゴンゾワラジを用いたと書いてあり、薮などにひっかからない乳なしのワラジが用いられたようである。
「御嶽の信仰と登山の歴史」-生駒勘七著(第一法規)

清滝
王滝口からの御嶽山登山道にある。不動様を祀った滝で、流れの中に不動様が浮かび上がるといわれている。
この滝で水行を積む。



新滝
厳しい寒さに凍てつく氷の造形は絶景。



四天 ⇒ 先達 ⇒ 中座 への道
- まず1年間は九字神宝、経文をひたすら覚えなければならない。
(経文は全部読誦するのに45分かかる)
- 2年間これを続けると、晴れて「四天」になることができる。
- 3年目から中座コースと先達コースに分かれ、
3年修行すると前座先達になる資格ができる。
- さらにこれ以上の修行を積んだ者が本座先達(神の託宣を誘導できる)となる。
- 中座(神を乗り移らせる)になる修行は最も厳しく、
これからさらに千日間(3年3ヶ月)
三業と称して、家業・水業・慎みの業の三つの業を積まなければならない。
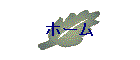


 登拝者の数はごくわずかなものであったことが知られる。
登拝者の数はごくわずかなものであったことが知られる。 


