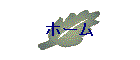

御 嶽 の伝 説
御嶽山頂の五つの池
ところがときどき人が登ってきては池を覗いたり、石を投げたりいたずらをするので、 龍はとうとう怒りだし、池を押し破って、 二、三、四、五の池を次々と造って各々別々に棲むようになったという。 これらは龍神伝説が伝わる神秘の池なのだ。 ニノ池は日本で最も標高の高いところにある高山湖、 三ノ池は日本の高山湖のなかでも最深の湖である。
継母岳と継子岳御嶽山の最高峰は剣ケ峰。 その両翼に控えるのが継母岳と継子岳である。 昔、京の白河宿衛少将頼永の子に阿古太丸という者があり、姉の利生御前とともに父母の寵愛を受けて成長していたが、母が突然の病で亡くなり、父は継母をむかえた。 ところが継母の岩永姫は、ことごとにこの姉弟につらくあたるので、阿古多丸はこの父母の家に住むことができず、父方の叔父にあたる奥州の中納言氏家を頼って、木曽路のこの地まで来た時、旅の疲れと病のために15歳の身で亡くなってしまった。 この山に 捨つる命は おしからで あかではなれし 父ぞ恋しき と、辞世の歌を残していったという。 父重頼と共に木曽に来た、姉の利生御前は、 先たつも 後るも同じ 草の露 何れの秋ぞ あはで果つべき の歌一首をのこし、弟阿古多丸のあとを追い、墓前で自害してしまった。このことを知った父重頼もまた、姫をねんごろにとむらい、初七日の後に、二人のわが子の墓前で自害し果てた。 さて風の便りにこのことを聞いた継母の岩永姫は、自分の所業のあさましさを悔い、京からはるばるこの地を訪れ、これまた墓前で自害したという。 臨終の際に自分を御嶽山へ葬ってくれという阿古太丸の願いを村人が聞き入れ、 阿古太丸の霊を継子岳に、岩永姫の霊を継母岳にまつったという。
十二権現様
男が御嶽山へ参詣して一心に祈願すると、その男から乳が出るようになり無事に子は育ったという。 御嶽山の霊験に感心した男は祠を建て、十二権現さまとしてまつった。 その後は安産子育ての神、子供を授かる神として今に及び参拝者も後をたたない。 また、いつの頃からか「猿ボコ」という小さな人形を供えるようになった。
神がかり御嶽信仰には「御座をたてる」と称する神がかりによる病気治療や卜占信仰がある。 それぞれの御嶽講社は中座・前座先達・四天などと呼ぶ行者を擁しており、 中座が神がかりをする巫者となる。 講中が経文をよむうちに中座に神がのりうつる。 四天は中座に悪魔があやまってとり憑かないよう、四方鎮めの役割をおい、中座を守護する。 神のお告げは先達を通して信者に伝えられ、病気治療やト占が主として行われていた。 医者にみはなされた瀕死の病人が生きかえった話とか、 神のおっしゃる通り、農作物が不作だった話、 卜占によって株の売買を行い巨利を博したという株屋の話など、 いわゆる奇蹟に類した話が数多く伝えられている。
ウォルター・ウェストンの眼一行の一人が、伸ばした手の掌のあいだに御幣を高く持ち、残りの人々は前の岩の上に坐っていた。 その残りの人々は彼と向き合いに坐って(その狭苦しい所で坐れるだけ近寄って)一列に坐っていた。 その彼の足は、日本人の坐る作法のように体の後に置かないで、ヒンズー人などのように前に組んでいた。 彼は、彼の友人たちと、その友人たちが神託を乞いに来た山の神々のあいだの、心霊交流の霊媒(日本の中座「中の座」)のような役をしていた。 目を閉じながら、この中座は静かに黙って坐っていた。 彼の仲間は急に押しつぶしたような声で祈りの合唱をやりかけた。 まもなくこの霊媒の顔は青ざめた色に変わり始めた。 この世のものとも思われないあえぎがのどを漏れ、御幣が手のなかで激しくふるえ動いた。 彼の目は、眼窩のなかで黒目が半分くらいしか見えなくなるまで、上のほうへあがってしまった。 痙攣的な激動が一わたりすむと、ついに御幣が彼の額の上で止った。 これは神様が降臨した印だった。 すると、このあいだじゅう、残りの人に対し音頭取りをしていた一人の巡礼者つまり前座(前の座)が、この霊媒の方に向ってうやうやしく平伏した。 彼の額を二人のあいだにあった岩の上に低くさげて、親しく降臨してこの霊媒に憑って来た神様の『お名前』を尋ねた。 するとしわがれた小さな声で、 『我は普寛霊神なり』 という答えがあった。 これは王滝側から、ちょうど一世紀前、御嶽へ最初にのぼって神に祀られた人のその死後の諡号なのである。 前座がその名を聞いた時、彼は5、6人の巡礼者たちの願い事を述べ出した。 それは皆ごく単純なものだった。 ある人は彼らの旅行中どんな天気に出会うかときいた。 あるいはまた家にいる家族の健康とか翌年のあいだの事業の予想についてきいた。 低い声で中座は神の答えを述べた。 これらの答えは、神託の場合にも通例であるように、都合のよいように、ぼんやりしたものだが、私はこの人がその日の午後は曇りだと予言したのを覚えている。 実際、私がこの予言を想い起したのにはもっともな理由があった。 というのは、このことがあって二、三時間ののち、私たちは無情な激しい雷雨を突いて、森の滑りがちな傾斜を急いで進んでいたからである。 尋ねた質問全部を断言するように答えてしまった時、霊媒の手にある御幣は、神霊が立ち去りその人がふたたび我に還った印に、下げられた。 すると前座は立ち上った。 そして彼は、全身昏睡状態だったあいだ非常に硬くこわばっていた中座の体を必要なだけ激しくさすり、手足を打ち始めた。 まもなくその人は正気づき、そのパーティは立ち去った。 彼らは、私がいることにまるでまわりの木立や石と同じように、なんの注意も払わなかった。 (「日本アルプス−登山と探検−」ウォルター・ウェストン著)
|
 大昔、御嶽山の一ノ池に、白籠、黒龍、赤龍、青籠、黄龍の五つの龍神が棲んでいた。
大昔、御嶽山の一ノ池に、白籠、黒龍、赤龍、青籠、黄龍の五つの龍神が棲んでいた。 昔、12人の子をもった男が妻に先立たれ、乳飲み子を養う乳がなく困り果てていた。
昔、12人の子をもった男が妻に先立たれ、乳飲み子を養う乳がなく困り果てていた。